どうも、太陽です。(No9)
突然ですが、「恋愛と戦争では手段を選ばない」ということわざが、イギリスにあるようです。
意味は「恋や戦争では、どんな方法でもすべてが正当化されるということ」とあります。
All’s fair in love and war。(英語)
このことわざから、「ビジネス方面などに応用してみよう」と思います。
興味がある方は、続きをお読みください。
1 恋愛と戦争ではフェアなルールはない。
「恋愛と戦争では手段を選ばない」という言葉があるようです。
どちらも共通点は命がかかっていることかもしれません。
恋愛も自分の遺伝子を残す戦争・競争であり、そこでライバルなどにひるんでいては「負けてしまう」ということでしょう。
戦争は文字通り、古来から命がけであり、その中で生き残ってきたのが今いる人類です。
その戦争の裏には、かなり非情な世界があったと思います。
命がかかっていますから、フェアルールなど通じません。
スポーツはフェアルールが比較的ありますが、恋愛と戦争ではフェアなルールはないと感じます。
恋愛では、弱者は傷つきます。
戦争では、弱者は死にます。
2 経済やビジネスの世界もフェアなルールが軽んじられてきている。
そして、最近では「経済やビジネスの世界も、恋愛や戦争と似てきているのではないか?」と僕は予測しています。
つまり、「フェアなルールが軽んじられてきているのではないか?」と。
ビジネスの世界は「スポーツに似ている」と捉える人もいるでしょう。
ですが、僕の認識ではどちらかと言えば、恋愛や戦争と似ています。
「ビジネスも弱肉強食になりつつある、または昔からなっていたのでは?」と。
出版界では「パクリが横行している」と推察されます。
他の世界はわかりません。
ですが、暗躍する産業スパイなどの話を聴くと、「ビジネスの世界も異常な世界になっている」と想像します。
さらに、恋愛系の記事では以下があります。
「LINEのスクリーンショットで彼を奪われた!文春砲レベルの恋敵のワナとは」というタイトル記事です。
恋愛では手段を選ばないの典型例でしょう。
LINEで浮気の証拠をねつ造された!カレを奪った恋敵のワナ | 女子SPA!
3 3つの空間。
ここで、3つの空間の話をします。
(話が飛びますが、ついてきてください)
僕は、この世界は概念的に「3つの空間に分かれている」と考えています。
まず1つ目が、親密空間。
家族や親友など利害関係なしに、付き合える間柄のことです。
そこには、そこまで損得の感情はありません。
たいていのことは話せるし、相手のために無償でいろいろと面倒をみてあげることもあります。
人間関係の距離で言えば「一番近い」です。
そして、この空間が充実していると、人は幸せを感じます。
2つ目は、利害空間。
文字通り、利害関係で成り立っている空間です。
損得やギブ&テイクで、基本的に動きます。
浅い友人関係や仕事の人が当てはまります。
込み入ったことはそこまで話せないし、お互いにギブ&テイクが成り立たないと、破綻します。
与えてばかりだと嫌になるし、受け取ってばかりだと、向こうが嫌になります。
距離はほどほどです。
「この空間との付き合いをいかに上手くやるか?」は人生の成功において重要でしょう。
3つ目は、金銭空間。
金銭でしか成り立たない空間です。
赤の他人なので、金を払わないと、情報や労働などを与えてもらえません。
あらゆるビジネス・サービスは、この空間です。
無償でやってもらうことは失礼です。
金をきちんと払わないといけませんし、相手側も金を貰うからには、きちんとサービスする義務があります。
もちろん、金額に応じたサービスになります。
高い金を払えば、高級サービスが受けられます。
距離は「遠い」です。
この空間では、あまり神経質になる必要はないので、ほとんど疲れません。
ただし、あまりに無礼な態度やクレームを取ると、相手側の印象が悪くなり、継続的にサービスを受ける場合、不利になることもあります。
無難な対応がいいでしょう。
もちろん、相手側のサービスにあまりにも理不尽さを感じたら、金を払っている以上、ある程度のクレームは許されるでしょう。
また、親密空間でもギブ&テイクがある場合もありますし、利害空間や金銭空間でも無償行為(ボランティア)などが、発生する場合もあります。
この3つの空間は、あくまで目安で、おおまかな枠組みと捉えてください。
そして、最後に主張したいのが、国家やメディアや大企業は諜報活動を通じて、「搾取している」と推測できる点です。
つまり、普通なら金を払ったり、親しい間柄にならなければ貴重な情報などを手に入れられないのに、奪ってしまうのです。
スノーデン氏の暴露が話題になりましたが、国家やメディアや大企業はおそらく、この行為をやっている可能性は残ります。
金も払わず、親しい人脈にもならないのに、奪っているかもしれません。
貴重な情報源を持っている人は注意した方がいいですが、国家絡みなら、個人での防衛はほぼ不可能ではないでしょうか。
「勝つためには手段を選ばない」のが「この世の常だ」と考えています。
戦争の場合は生死が懸かっているので、特に当てはまりますが、経済戦争(ビジネス)でも起こっているでしょう。
「勝つために手段を選ばない」ことを汚いこと、不公平だと唱えることはできますが、人間の世界とは、そもそもこういう世界で、汚い世界だと捉えておいた方が正しいかもしれません。
スポーツではルールがあり、公平さはある程度保たれています。
ですが、戦争やビジネスの世界では一応ルールはあっても、表向きに過ぎず、理不尽さで溢れていることでしょう。
そういう世界を勝ち抜いていくためには、セキュリティなどの防衛意識は当然、必要です。
「相手がフェアプレーをする」と思わない方がいいでしょう。
映画の世界ですが、「デスノート」では国家の危機ということで、ライトという容疑者を盗聴・盗撮している場面があります。
「これが勝つためには手段を選ばない」という一例であり(フィクションですが)、スノーデン氏の暴露では、本当に現実でした。
戦争やビジネスでは、ルールはあってないようなものと、考えておいた方がいいかと思います。
この話題については「超監視社会」という本に詳しく書かれています。
アメリカ企業の製品に、バックドアを仕掛けて、後で遠隔操作できるようにしたり、ソフトの脆弱性をNSAなどは知っていますが、わざと修正せず残しておき、監視に利用します。
しかし、脆弱性は、他社や他人も調べる能力があれば見つけることができるので、もろ刃の剣です。
脆弱性は、NSAだけが利用できるわけではなく、他者も見つけられます。
ソフトの脆弱性を残さなければ、ソフトのセキュリティは高まりますが、NSAは監視に利用できなくなります。
そして、今のところ、NSAは脆弱性を独自の判断で残しているようなのです。
そこには、僕たちのセキュリティの向上やプライバシー保護という観点が抜け落ちています。
今の状況下においては、NSAや他のハッカーらは、僕たちのPCやスマホなどをハッキング可能なのです。
これは夢物語でもなんでもなく、脆弱性やバックドアが残っている限り、起きている現実です。
(しかも、わざと脆弱性やバックドアを残しています)
つまり、やろうと思えば、NSAはもちろん、脆弱性を見つけたハッカーらによって、僕たちの情報は筒抜けになるのです。
この怖さを「まずは認識した方がいい」と思います。
インターネット時代においては、ハッキング、盗聴・盗撮、プライバシーの漏洩、情報の漏洩などは、当たり前の時代なのです。
ちなみに、「ダック・ダック・ゴー」という検索エンジンは検索履歴を残さないし、「ウィッカー」というメッセージアプリはメッセージを強力に暗号化してやり取りでき、「エロー」は利用者の個人情報を収集しないSNSです。
これらは、プライバシーを重視したビジネスモデルで、差別化を行っています。
NSAの監視活動が暴露されたことにより、アメリカ企業のウェブサービスの利用や製品やネットワーク機器の購買、アメリカ企業の信用に、疑心暗鬼が生まれています。
NSA内部でも、監視の乱用が起きています。
例えば、NSAの職員は日常的に国内のアメリカ人の私的な通話を盗聴してますし、電子メールも傍受し、性的な画像を同僚の間で閲覧しています。
さらに、NSA職員が「みずからの知人の通信を傍受している」という情報まであります。
もはや、NSA自身も、権力の乱用が止まりません。
また、パノプティコンという看守が塔の上から監視しているかもしれないという圧力によって民衆は、「もしかしたら見られているかもしれない」と思い込み、身動きが取れなくなります。
看守はいつも見張っているわけではないのに、民衆には効果抜群なのです。
NSAの監視も同じような効果があります。
僕たちは、このような超監視社会を生き抜いていかなければならないというわけですね。
スノーデン氏に興味がある人は以下の映画や本がオススメです。
恋愛・結婚市場を中心に分析しており、ナンパ市場は分析していませんが、男女の非情な世界を科学的に描いているのが以下の本です。
「彼と彼女の科学的恋愛診断―――結婚するか別れるかは、つき合う前からわかっている」
残酷な世界で生き抜いていくには、ある程度、相手のウソを見破れないといけません。
そのための手法が書かれている本が以下になります。
元知能犯担当刑事の長年の経験からくるウソを見破る技術ですから、かなり有用です。
ではこの辺で。(4109文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。
引用・参考文献。








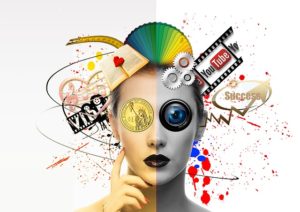

コメント