どうも、太陽です。(No65)
 悩み人
悩み人離婚率3割といわれ、約「3人に1人」は離婚している昨今。
「マジで離婚したい!」という人はいるよね?
そんな人のために、僕が「弁護士さん とにかく分かりやすく離婚について教えてください!」という本を参考にしてまとめたのが今回の記事になります。
あくまで、「離婚の流れ・概要を掴むための記事」です。
細かい規則などは、「ぜひ本を読んでもらえたら!」と思います。
このテーマに興味がある人は続きをぜひ読んでください。
1 マジで離婚したい人へ。離婚の流れ。
まず、離婚の流れとしては、以下になります。
夫婦で話し合い。合意できれば、協議離婚。
↓ 合意できなかったら、
↓
離婚調停。調停成立すれば、調停離婚。
↓
↓ 調停不成立になれば、調停に代わる審判。(審判離婚)
↓ または、
離婚訴訟。(和解・認諾・勝訴)などを経て、裁判離婚。
↓
↓ 敗訴すれば、
離婚不成立。(控訴、上告がなされる場合あり)
日本の離婚の9割は「話し合い」による協議離婚です。
なので、「まずは話し合いを目指しましょう!」という結論になります。
裁判で離婚できないケースもあり、民法770条に確定されている5つの理由に当てはまるかどうかだけが問題になります。
(これを法定の離婚原因と言うのでしょうかね?) 詳しくは本で。



協議離婚なら、法定の離婚原因は必要ないので、「まずは話し合いましょう!」ということに尽きるのかぁ。
離婚の際、話し合う項目として、以下があります。
| 1 | 慰謝料。 |
| 2 | 財産分与。 |
| 3 | 婚姻費用と別居の注意点。 |
| 4 | 子供がいる場合、親権問題。 |
| 5 | 養育費。 |
| 6 | 面会交流権の問題。 |
協議離婚の場合、「話し合い」なわけであり、交渉術が必要なので、よく研究してください。
1の、慰謝料は損害賠償なので、離婚原因を相手が作った場合でなければ貰えません。
離婚原因を作った方(=有責配偶者)が相手方に支払うのが慰謝料です。
詳しくは本で。(「慰謝料には時効がある」ので注意してください)
2の、財産分与は「結婚した後に夫婦で協力して築いた財産を分けること」です。
財産には「特有財産」(夫婦が協力して作った財産じゃないもの)と「共有財産」(財産分与で分けるのはこちら)があります。
結婚前の貯金は、特有財産だから、奪われません。
年金や退職金も「財産分与の対象」となります。
また、不動産の財産分与の場合には、登記手続の際の登録免許税と、その後の固定資産税が課税されます。
税金についてはごちゃごちゃしているので、詳しくは本を読んでください。
「共有財産は2分の1ずつの割合で分けるケースが多い」ことは知っておくといいです。
財産分与については「どちらが有責か」は関係ないですが、財産分与も年金分割も時効は離婚成立から2年なので、注意が必要です。
3の、婚姻費用とは「生活費のこと」を言います。
「お互いが同レベルの生活ができるように協力する義務」があるので、収入のある方が無い方に対して、生活費の支払いをする義務を負います。
(専業主婦は助かる仕組み)
婚姻費用は「離婚成立するまでの費用」です。
で、離婚成立後は相手の生活を見る必要がないので、子供がいる場合は、子供の養育費だけになります。
別居も絡んでくる場合があります。詳しくは本で。
4の、親権はけっこう揉める問題です。
親権は、簡単に言うと、「未成年のお子さんの利益のために、親がお子さんを養育、監護する権利であり、義務のこと」を言います。
親権を決めるうえで一番重要視されるのは、監護の継続性、つまり「それまで日常的に面倒を見てきたかどうか?」です。
育児を手伝わない男性なら、まず親権は取れません。
親権は一度、決めると、後で変更するのがかなり大変なので要注意事項です。
5の養育費は、「子供を養育するためのお金」です。
子供がいて育てている側が、養育費を貰えます。
親権を得て、離婚後にお子さんと生活する人が、相手に請求するのが養育費です。
なので、例えば、妻が子供と暮らすなら夫が払いますし、夫が子供と暮らすなら妻が払うのが原則です。



養育費は、母子世帯で養育費を現在も受給している世帯は、養育費の取り決めをしている世帯で53.3%、取り決めのない世帯も含めると、24.3%なので、4人に3人は支払われていないね。
養育費を貰えるのは4人に1人なので、養育費はあまり当てになりません。
(社会問題化しています)
公正証書を作っておけば、強制執行もできます。
協議離婚なら、養育費だけでなく財産分与、慰謝料等、離婚時に決めた金銭にまつわることは全て、公正証書にしておくとその後の対応が楽になります。
公正証書とは、「公証役場に行って公証人に作ってもらう証書のこと」を言います。
他には、離婚調停で離婚成立した場合は、「調停証書」をつくるので、養育費も決めてあれば、それに基づいて家庭裁判所の履行勧告、履行命令、強制執行が受けられます。
履行勧告は、裁判所が相手に「支払って下さい」と勧めてくれることであり、履行命令の場合は従わないと過料(かりょう)が科されます。
履行勧告は裁判所が「〜してください」と促すだけですが、強制執行は給与や預貯金を強制的に差し押さえることができるので、養育費を貰える可能性が高まります。
6の面会交流権とは、「子供と離れて暮らす側の親が子供と会う権利のこと」です。
(お子さんが親に会う権利でもある)
ちなみに、「面会交流と養育費は別の話」なので、養育費を払っていないからといって、面会交流を拒むことはできません。
詳しくは本を読んでください。
2 マジで離婚したい人へ。その他の事項。
「離婚後の氏をどうするか?問題」がありますが、詳しくは本を読んでください。
(けっこう複雑)
「女性は離婚後100日以内は再婚できない」という再婚禁止問題があります。
「父親が誰か」という混乱を防ぐためにあります。
「この法律は変えよう」という方向性にあるようです。
3 マジで離婚したい人へ。協議離婚の準備 証拠編&実践編。
協議離婚は話し合いであり、ある意味、交渉術が必要です。
そのためには「証拠がある」と強いです。
詳しくは本を読んでください。
協議離婚(話し合い)の流れは以下になります。
| 1 | 今後の生活について考える。 |
| 2 | 離婚を切り出し離婚条件を話し合う。 |
| 3 | 決まった内容を元に離婚協議書または離婚公正証書をつくる。 |
| 4 | 離婚届を提出する。 |
詳しくは本で。
要注意点として、不安があるときは、離婚届の不受理届を出しておくのも忘れないようにしてください。
離婚届けの不受理届とは、「離婚届を役所が受け付けないようにする届け出のこと」を言います。
離婚自体には合意しているけれど離婚条件がまとまっていないケースで、一方的に離婚届を出されてしまう恐れがある場合や、離婚届けに強引にサインさせられた時に、必要です。
偽造して提出した離婚届は、有印私文書偽造ですが、喧嘩の際等に「とりあえず書いた」離婚届を勝手に出されてしまうケースがけっこうあります。
他にも詳しく書かれているので、ぜひ読んでみてください。
以上、「弁護士さん とにかく分かりやすく離婚について教えてください!」の本をまとめました。
さらにこの本を一読して理解した上で、以下の本を読むと、尚、理解が深まるかもしれません。
マジで離婚したい人は読んでおくといいかもです。
第5版まで出版されており、長年、評価されてきた定評のある本なのでしょう。
ただし、僕がまとめた本は会話形式になっていましたが、第5版の本は会話形式じゃないので、とっつきづらいと思います。
最初の1冊目としては、僕がまとめた「弁護士さん とにかく分かりやすく離婚について教えてください!」の本がお勧めです。
4 最後に。
最後に、ひかりん@婚活菩薩さんのツイートを貼ります
現在の日本の法律では結婚後に稼いだお金は夫婦で折半、離婚調停中は生活費を払い続ける必要があります。
これを利用して高収入の男性と結婚して2〜3年で別居し、離婚裁判を長引かせ夫の独身時代の資産数千万以上を奪うことを最初から目的にして結婚する女性がいるので高収入男性は気をつけて下さい



最初から離婚と裁判狙いで、別居もして、生活費を払わせ続け、寄生する女性がいるのかぁ。
ただ、35歳で資産3000万で、仮に結婚したなら、その後の結婚生活で築いたお金だけが財産分与の対象になるわけです。
ですが、離婚裁判に持ち込み、別居し、生活費を払わせ続け、資産3000万円が徐々になくなっていくのは可哀想ですね。



そもそも協議離婚が9割なのに、1割未満の離婚裁判まで持ち込む時点で、確信犯じゃないか?
(かなりの少数派の悪魔のような女性だね)
加えて、僕の短文書評も載せておきます。
「「弁護士さん とにかく分かりやすく 離婚について教えてください!」
3.5点。
会話形式で進んでいくので、非常に理解しやすい。
離婚について考えているのなら、まずはこの本を読むのがお勧めだと思った。
詳細な数字やいろいろな秘訣などが書かれており、かなり参考になる本。
最後に、離婚しやすい人の特徴を、メンタリストDaiGoが紹介しているので、予防したい、離婚したくない人は見ておきましょう。
離婚しやすい人の共通点【男女で違う】
僕のブログは婚活・恋活ブログなのですが、万が一のことも考え、離婚記事も扱いました。
こんな不幸じゃない話題・内容の記事も載っているので、ぜひ読んでみてください。
https://lovehacksalon.osusume-etc.com/
ではこの辺で。(3985文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。
参考・引用文献。








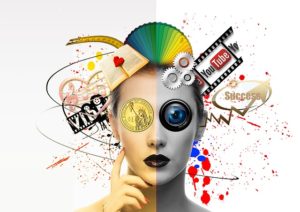

コメント