どうも、太陽です。(No23)
突然ですが、前回までに「コミュニケーションの基本」編を書きました。

コミュ力の上げ方「コミュニケーションの基本」
さらに、「雑談編」もあります。
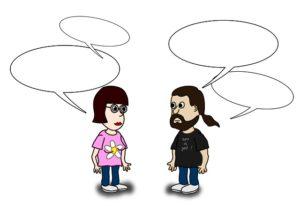
コミュ力の上げ方「コミュニケーションの基本 雑談編」
今回は「コミュニケーションの達人」編を書きたいと思います。
興味がある人は続きをお読み下さい。
1 他己分析の大事さ。
まず、コミュニケーションの基礎として「自分と人は別物」という意識が不可欠です。
人間はどうしても自分の感覚や感情などから、「自分がこう思っている・感じているなら、相手もそう思っている・感じているに違いない」と思いがちです。
ですが往々にして、その認識は間違っています。
僕たちが思うように感じるように、他人も思い・感じていません。
そう考えると、他人を他己分析する必要が出てきます。
自分とは違う人間を、タイプ別にある程度類型化して、目安をつけて接するのです。
そこで役立つ類型化として、エニアグラムが挙げられます。
詳しくは以下の記事を読んでください。お勧めの本も紹介しました。

「エニアグラムで人間関係を改善!人間の動機付けは人それぞれだ」
他己分析することにより、他人をある程度は目安として類型化でき、なんとなくですが把握することができます。
エニアグラムの診断テストは以下からできます。
実は、当時、この記事を書いていた頃にあったエニアグラム診断サイトが消えました。
ですので、上記のサイトは新しいサイトです。
なので、以下に続く文章では、文脈上、意味がおかしい箇所が出てきます。
(以前のサイトの文章を引用しているので。もう、そのサイトは消えましたからね。でも、書かざるを得ないので、仕方なくそのまま載せます)
話を戻します。
この診断テストを受けた人で、多くの人が言いがちなのが、「これ、誰でもそうじゃね?当てはまるよね?」という意見です。
例えば、8番目の質問の「個性的であることやユニークさを発揮することは何より大切だと思う」という項目に、チェックを入れるべきか迷う人がいます。
何よりという部分に引っかかり、「何よりということは1番という意味だよね?」と言い、「ある程度は思うけど、そこまでじゃない場合はチェックを入れるべきなのか、そうじゃないのか?」と言うのです。
この疑問については、エニアグラムタイプ4の人(芸術家)は本当に個性やユニークさを第一に考えており、迷わずチェックを入れる傾向にあります。
ですので、この質問をした人(迷った人)は「タイプ4の素質が弱い」ということになります。
他にも、いろいろな質問で揚げ足を取る人がいます。
そういう人は「この質問、誰でも当てはまるよね?」や「されて嫌なことって、これも誰でも当てはまるよね?」というのです。
これはこの人の価値観や世の中の人間への認識力が乏しく、世の中には自分の想像以上にいろんな人がいることが分かっていないのです。
で、「自分がそう思うのだから、他の人もそうに違いない」と思い、主張してしまうのでしょう。
ですが、世の中にはエニアグラムでいう、タイプ9つの特徴を強く持った人がいて、多様なのです。
自分の価値観や物差しだけで測るべきじゃありません。
こういう愚問を言う人は正直なところ、「人間への認識力が弱いのか、文章読解力が低い」の、どちらかだろうなぁと検討がつきます。
自分の物差しや価値観で人間を見ないことが大事であり、「自分と人は別物」という意識が重要です。
2 コミュ力は場面や役割別に求められる能力が異なる&人によって対応を変える。
コミュ力は場面や役割別に、求められる能力が異なります。
| 1 | 上司としてのコミュ力 |
| 2 | 親としてのコミュ力 |
| 3 | プライベートの友達(同性中心)のコミュ力 |
| 4 | 異性とのコミュ力 |
| 5 | 各仕事(業種、職種によりバラバラ)でのコミュ力 |
など というふうに、場面や役割別に求められるコミュ力は異なるのです。
これをまず、頭に入れておいてください。
次に、場面や役割別とは別に、人によって対応を変えることが有効なことが多いです。
カメレオンのように人によって、千差万別に対応や態度を変えられるのがコミュ力強者です。
例えば、エニアグラムなどによって、人のタイプを見極め、対応や態度を変えるのです。
他にも、その人の個人情報を入手すれば、対応を変えやすいでしょう。
これが2点目です。
つまり、場面や役割や人によって、柔軟に対応や態度や言動を変えられるからこそ、多様な人と交わることができ、目的(交渉や親睦など多数)を達成できるのです。
他己分析で、他人に応じてコミュニケーションを変えないといけない上に、場面や役割でも変えないといけないからこそ、コミュ力は複雑系なのですね。
ですが、演技をするということは、自律神経に負担をかけ、精神的にまいってしまうので、プライベートでは素の自分でいられる相手と付き合うべきです。
プライベートでは、自分に正直に生きた方がいいです。
(仕事でも自分に正直に生きれる環境を作れるなら、そうするに越したことはありません)
人によって対応を変えるのは、仕事や交渉事など場面や役割が中心であり、プライベートまで引きずるときつい人生になります。
仮面をかぶる、自分を偽らざるを得ないのが人生ですが、プライベートまで偽る必要はありません。
3 外交型か内向型か両向型かを判断。
ここで、人には外向型と内向型と、その中間の両向型があり、それぞれのタイプで交友関係の仕方が異なります。
エニアグラムと役割や場面別を覚えておいて、さらに外交型か内向型か、両向型かの大まかな目安を考えておきます。
外交型は「広く浅く」です。
内向型は「狭く深く」です。
両向型はその中間くらいです。
この相手との距離感というのも、コミュ力にとっては重要な要素になります。
「相手がどのような距離を望んでいるのか?」で、こちらの対応を変える必要があるからです。
例えば女性であれば、ある男性を「友達設定」にしているとします。
で、男性側は「恋人になりたい設定」に女性を置いていたら、口説いたり、接近しようとするでしょう。
ですが、女性側は「友達設定」なわけですから、距離をほどほどにしたいわけです。
その結果、男性からしたら「なぜ、接近しようとすると連絡が少なくなるんだ?」と不思議がることになります。
これは同性間でも同じです。
「親友や深い関係になりたい設定側の人」は深く接しようとします。
ですが、相手側は何かの目的(仕事や趣味など)でつながりたいだけだったり、そこまで深く仲良くなりたくない設定にしたら、深く付き合う設定側の距離の詰め方は嫌なのです。
「どういう距離感を相手が求めているのか?」を把握しておかないと、ストーカーになったり、嫌がられるのです。
相手は「頻繁に連絡しないでくれ!」というメッセージを発するはずなので、それを察知し、気づくことが大事です。
人間は深い付き合いをできる人数は限られます。
誰でもそうです。
相手側の深い付き合い人数の範囲内に入れなかった場合、違う人を探すか、距離のとり方を考えるべきなのです。
最後にメンタリストDaiGoとエニアグラムの本を紹介して終わりとします。
(エニアグラムを深く理解すると、人間づきあいがしやすくなります。ちなみにエニアグラムに科学的根拠はありませんが僕の好みで紹介しています)
3点。
前半より、中盤から後半に渡って質が濃くなる珍しい構成の本。
前半は雑談や話し上手になるコツについて、後半は親睦を深めるための話し方のコツや、会話に悩む人、会話がうまく回らない人への改善のコツが書かれていた。
後半の方で悩んでいる人が多そうな印象。話し上手、話し下手両方の改善に効果がある本。」
以上、ここまで。
ではこの辺で。(3517文字)
このブログは個人的見解が多いですが、本・記事・YouTube動画などを元にしつつ、僕の感性も加えて、なるべく役立つ・正しいと思われる記事を書いています。
あくまで読者がさらに深く考えるきっかけとなればいいなぁという思いですので、その辺は了解ください。










コメント